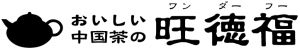お気に入りの茶葉を手に入れ早速淹れてみたあなた。「う~ん、やっぱり春の新茶は香りが清々しい・・・。」
買って来た茶葉は50g。次回お茶を淹れる時までどのように保存すればいいんだろう?
コラム「お茶の壷」第10話
中国茶・台湾茶のおいしさを保つ茶葉の保存方法についてお話ししましょう。
サイト内「中国茶の基礎知識」でも簡単にご案内していますが、ここではもう少し深く掘り下げてみます。
保存方法を知るためには、まず茶葉の性質・特徴について知っておく必要がありますね。
一般的に茶葉は吸湿性、酸化、においの吸着性を持っています。そのため茶葉は湿度、温度、空気、光を含む周辺環境の作用によって、茶葉に含まれる多くの化学成分が変化することで劣化し、風味が損なわれてしまいます。
・茶葉の吸湿性
茶葉には人の血管のように毛細管がはりめぐらされています。また、茶葉には親水性のある多糖化合物が含まれています。そのため空気中の湿度が高くなると、茶葉は水分を吸収してしまい、茶葉内部の水分含有量が増えていきます。
・茶葉の酸化
茶葉の酸化とは茶葉が劣化すると言うことです。茶葉内部に含む水分含有量の増加や保存環境の温度が高いなどの条件のもとで茶葉の酸化がおこりやすく、酸化がはじまると茶葉の変質速度が速まります。
・茶葉の吸着性
茶葉の毛細管にはにおいを吸着する特性があります。保存中に他のにおいのあるものと一緒にすると、茶葉はそのにおいを吸着してしまいます。
茶葉は水分やにおいを吸着しやすく酸化しやすい特徴を持つことがわかりました。
では茶葉のおいしさを保つために気を付ける保存環境について考えてみましょう。茶葉の変質と劣化の原因は茶葉の中にある化学成分の酸化によるものです。この酸化を引き起こす主な要素は空気中の湿度、温度、酸素、光(紫外線)の四つです。
・湿度
茶葉は水分を吸収しやすいため、湿度が高くなれば水分をより多く吸収します。茶葉の水分含有量が増加すると、クロロフィルが溶出し、ポリフェノールの酸化と、酵素と酸素による反応が進みます。水分を多く含み過ぎた茶葉は、味が薄くなり香りが消え、品質が低下してしまいます。
・温度
保存環境の温度が高くなればポリフェノールの酸化など化学反応の進行が速まり、茶葉の品質が低下します。
・酸素
酸素は茶葉内部の元素と反応し、脂質類が酸化重合することで茶葉の劣化を進めます。
・光(紫外線)
光は茶葉内部の各成分の化学反応を進行させ、色素を酸化変性させます。
茶葉のおいしさを保つ保存方法。これでもうお分かりですね。
茶葉を劣化させる、湿度、温度、酸素、光、この四つの要素を取り除くことです。おすすめの保存方法をご案内します。
①茶缶での保存
密閉度が高く光を透さない茶缶を使いましょう。茶缶は清潔を保ち、茶缶に異臭がないかよく確認してから茶葉を保存します。シリカゲルなどの防湿剤を入れておくのも効果的です。おすすめはページトップの画像にある錫製の茶缶。錫は密閉度が高くイオン効果もあって、茶葉の保存には最適です。(値段がちょっと・・・)
茶缶の口径は茶葉を取り出しやすい大きさを選びましょう。必要量の茶葉を取り出したら出来るだけ早く蓋をします。空気に触れる時間を少なくすることがポイントです。熱源の傍など温度が高くなる場所を避ければ常温で大丈夫!
②冷蔵庫での保存
冷蔵庫で茶葉を保存すると品質の劣化がゆるやかで、茶葉の鮮度を保つことができます。ただし注意すべきことがります。
一つは”密閉度”。茶葉を入れる容器や袋がしっかりと密閉できることが重要です。密閉度が低いと、保存中の茶葉自体が冷蔵庫内の脱臭剤になってしまいます。茶葉はにおいの吸着性が高いことを忘れないでください。
もう一つは、冷蔵庫で保存していた茶葉をお使いになる時には、冷蔵庫から出してすぐに容器や袋から茶葉を出してはいけません。しばらく常温にならしてから茶葉を取り出しましょう。これは、冷蔵庫内で冷たく冷やされた茶葉と容器・袋を冷蔵庫内から取り出してすぐに容器の口を開くと結露が起こるからです。一気に風味が落ちて行きますのでご注意ください。
③茶壷での保存
通な方におすすめ。茶壷や瓶の中の外周部に包装された茶葉を置き、中央部には布袋に入れた石灰を置きます。石灰は湿気を吸収してくれますので、容器内の水分を調整してくれます。長期の保存が可能です。
おいしい中国茶の旺徳福では、アルミ製のパッケージに茶葉を入れて販売しております。チャック付きですので、必要量の茶葉を取り出したら出来るだけ空気を抜いてシールします。そのまま常温で保存できるのでとっても便利。そして茶葉を買うときは出来るだけ小袋の容量がおすすめです。例えば100g買う場合には、50g入りを2袋にすると、最初の一袋目を開封しても別の袋の50gは空気に触れずに保存できます。

※カメラ故障中のため画像はイマイチですが・・・